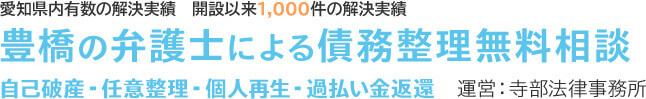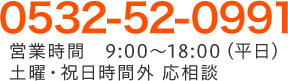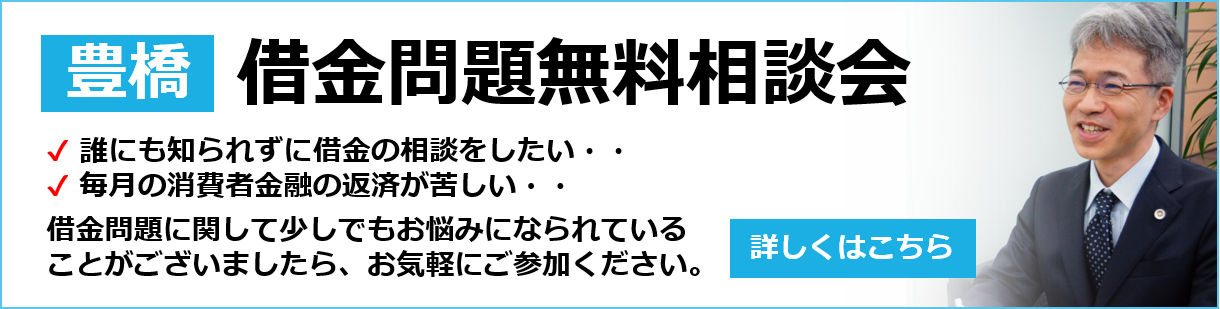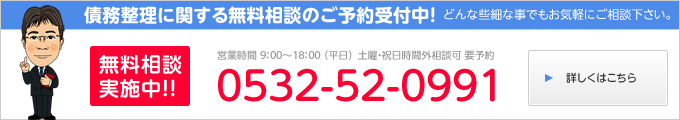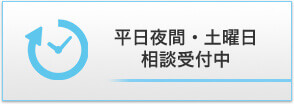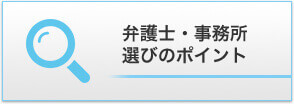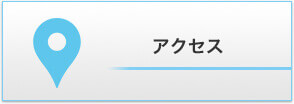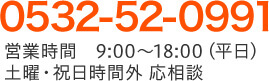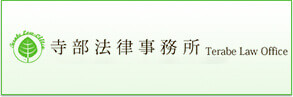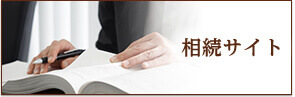【コラム】相殺禁止規定に違反する相殺を有効とする合意の効力
| 破産法71条、72条は、相殺禁止を定めています。
その趣旨は、債権間の実質的平等を図るところにあると考えられます。
それでは、破産管財人と破産債権者の間で、相殺禁止規定に該当する相殺を有効とする合意をすることはできるのでしょうか。 |
 |
この問題に関し、最高裁判所の裁判例では、
「破産債権者が支払の停止を知ったのちに破産者に対して負担した債務を受動債権としてする相殺は、破産法上原則として禁止されており(同法104条2号)、かつ、この相殺禁止の定めは債権者間の実質的平等を図ることを目的とする強行規定と解すべきであるから、その効力を排除するような当事者の合意は、たとえそれが破産管財人と破産債権者との間でされたとしても、特段の事情のない限り無効であると解するのが、相当である。」旨判示したものがあります。
「破産債権者が支払の停止を知ったのちに破産者に対して負担した債務を受動債権としてする相殺は、破産法上原則として禁止されており(同法104条2号)、かつ、この相殺禁止の定めは債権者間の実質的平等を図ることを目的とする強行規定と解すべきであるから、その効力を排除するような当事者の合意は、たとえそれが破産管財人と破産債権者との間でされたとしても、特段の事情のない限り無効であると解するのが、相当である。」旨判示したものがあります。
なお、この裁判例中の破産法は、平成16年法律第75号による改正前破産法を指し、104条2号は、現破産法71条1項3号がこれに相当します。
また、この裁判例では、相殺が無効である旨の結論となっています。
個人的には、実務において、破産管財人と破産債権者との間で相殺禁止規定に該当する相殺を有効とする合意をすることは、極めてまれなことだと思います。
破産手続きにおける相殺禁止についてわからないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
コラム一覧
当事務所の弁護士が日々感じていることをコラムにしています。こちらもご覧下さい。

お気軽にご相談下さい!
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
事前にお電話にて相談日のご予約をお願い致します。債務整理のことならお任せ下さい。 ※お電話での相談は行っておりません。ご予約のみとさせていただいております。ご了承下さい。