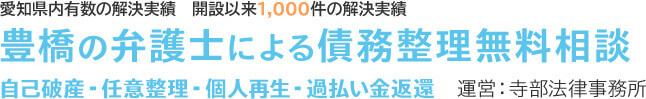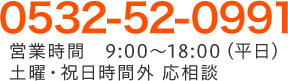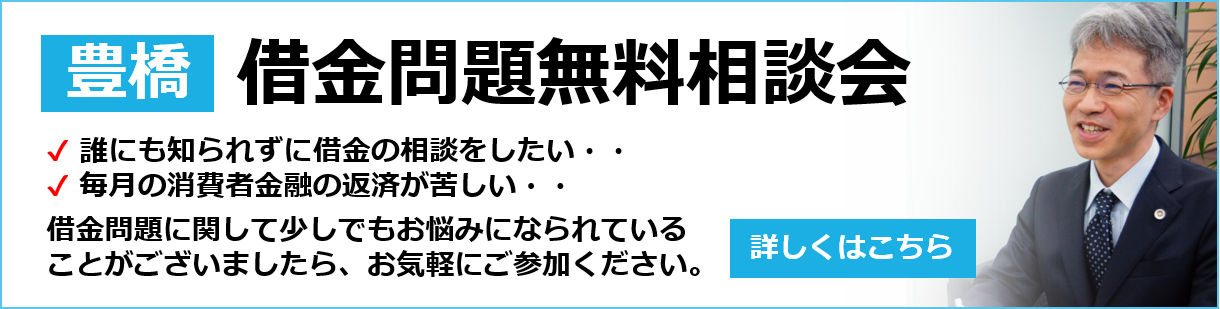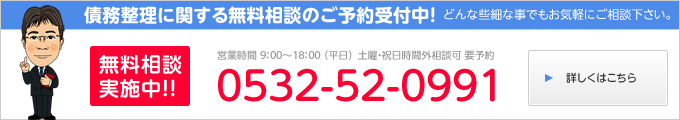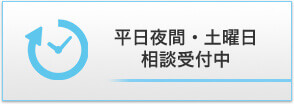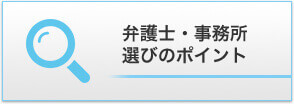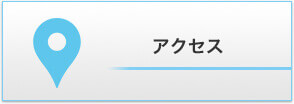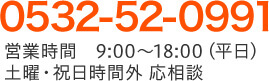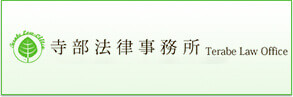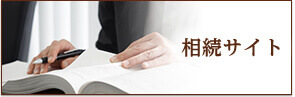自己破産の手続に向けて必要な書類とは?
1 はじめに
自己破産の申立をするにあたり、どのような書類が必要になるのでしょうか。
自己破産の申立をするにあたり、申立書、財産目録、家財道具等目録、債権者一覧表、滞納税金等一覧表、家計の状況、陳述書等の書類や添付資料が必要になります。
また、破産申立には、収入印紙や切手を添付する必要があり、予納金を納付する必要があります。
それでは、自己破産の申立には、どのような資料(書類)を添付する必要があるのでしょうか。
2 自己破産に必要な基本的な書類
自己破産に必要な基本的な書類は、住民票、収入に関する書類、財産に関する書類、負債に関する書類などです。
なお、自己破産の申立に必要な書類は、事案によって異なります。個別の事案については、弁護士までご相談ください。
3 収入に関する書類
(1)会社員の方
源泉徴収票(2~3年分)、給与明細(2~3か月分)が必要になることが通常です。
源泉徴収票の入手の困難な場合には、所得証明書を市区町村役場にて取り寄せていただく場合もあります。
(2)年金収入のみの方
源泉徴収票(2~3年分)、受給している年金額の分かる書類が必要になることが通常です。
(3)主婦の方
所得証明書(2~3年分)が必要になることが通常です。
収入がゼロの場合でも、収入がゼロであることを証明するために、所得証明書が必要になります。
(4)自営業(個人事業主)の方
確定申告書(2~3年分)が必要になることが通常です。
4 財産に関する書類
(1)預金
通帳(1年分の取引履歴の記載のあるもの)の写しが必要になることが通常です。
通帳の取引履歴にまとめ記帳がある場合には、まとめ記帳の分の取引履歴が必要になることが通常です。
ウエブ通帳の場合には、1年分の取引履歴をプリントアウトしたものが必要になることが通常です。
財形貯蓄をされている方については、積み立て状況やその残高等が分かる書類が必要になることが通常です。
(2)賃貸不動産に居住されている方
賃貸借契約書の写しが必要になることが通常です。
会社の寮に居住されている方の場合、入寮証明書など、会社の寮に居住していることが分かる書類が必要になることが通常です。
(3)自己所有の持ち家に居住されている方
固定資産評価証明書、不動産全部事項証明書(共同担保目録付)が必要になることが通常です。
持ち家に居住されている方について、不動産全部事項証明書(登記簿謄本)を取得される場合には、共同担保目録付で取得することが必要になります。
(4)自動車を保有されている方
自動車検査証の写しが必要になることが通常です。
自動車ローンがない場合、自動車の年式等によっては、査定書を取得していただく場合があります。
(5)保険契約をされている方
保険証券が必要になることが通常です。
解約返戻金の証明書が必要になる場合があります(保険証券に解約返戻金がないことが明示して記載されている場合や、月払いの自動車保険などでは、解約返戻金の証明書が不要になる場合もあります)。
(6)退職金
退職金の金額の証明書が必要になることが通常です。
(7)株式を保有されている方
取引残高報告書などの残高が分かる書類が必要になることが通常です。
(8)持株会に加入している方
持株会発行の持ち株数の分かる書類などが必要になることが通常です。
(9)信用金庫、信用組合の出資証券をお持ちの方
出資証券が必要になることが通常です。
(10)過去に処分した財産がある方
①不動産を売却したことがある方
過去に売却した不動産がある方については、売買契約書、全部事項証明書(共同担保目録付)が必要になることが通常です。
②自動車の売却
過去1年以内に自動車を売却したことがある方については、売買契約書の提出が必要になることが通常です。
③保険の解約、解約返戻金の受領
過去1年以内に保険を解約し、保険の解約返戻金を受領したことがある方については、解約返戻金の受領を証する書面が必要になることが通常です。
5 負債に関する書類
債務の残高が分かる書類が必要になることが通常です。
なお、税金の滞納がある場合には、滞納税の金額が分かる書類が必要になることが通常です。
6 弁護士に依頼をした場合
(1)受任通知の発送
当事務所では、自己破産のご相談を受けた方について、弁護士が面談をして、必要な書類について、ご説明をさせていただいております。
当事務所では、ある程度の資料を集めていただいた段階で、ご依頼を受け、債権者に対し、受任通知を発送しています。
受任通知を発送すると、債権者とのやりとりは、原則として、弁護士を通じて行われます。
(2)受任通知の発送後の資料の収集
当事務所では、受任後も、定期的に面談をさせていただき、家計の状況を確認させていただいたり、資料の内容を確認しながら、追加で資料の提供をお願いさせていただいたりしています。
当事務所では、不動産全部事項証明書(共同担保目録付)など、当事務所でも取得できる資料については、ご要望に応じて取り寄せることもできますが、当事務所で取り寄せることができない資料も多く、ご依頼者の方に取り寄せをお願いしています。ご理解とご協力をお願いいたします。
(3)負債に関する資料
負債に関する資料については、お手元にない場合でも、当事務所が、受任通知を発送後、債権者から債権届出書や取引履歴を取り寄せます。
(4)申立書等の作成
破産申立書、財産目録、家財道具等目録、債権者一覧表、滞納税金等一覧表は、ご依頼者の方の申告や資料に基づき、当事務所において、作成します。
陳述書は、ご依頼者の方の申告に基づき、当事務所において作成し、ご依頼者の方に確認していただいたうえで、ご署名、ご捺印をいただいております。
家計の状況は、ご依頼者の方の申告に基づき、当事務所において、作成します。
破産申立をした後、裁判所から、追加の資料の提出を求められる場合があります。
弁護士を依頼した場合、裁判所とのやりとりは、原則として、代理人である弁護士を通じて行われます。
追加の資料の提出を求められた場合、弁護士から、ご依頼者の方に追加の資料の収集をお願いしています。
7 まとめ
自己破産の手続について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
お気軽にご相談下さい!
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
事前にお電話にて相談日のご予約をお願い致します。債務整理のことならお任せ下さい。 ※お電話での相談は行っておりません。ご予約のみとさせていただいております。ご了承下さい。